
まずは産後うつについて教えていただけますか?

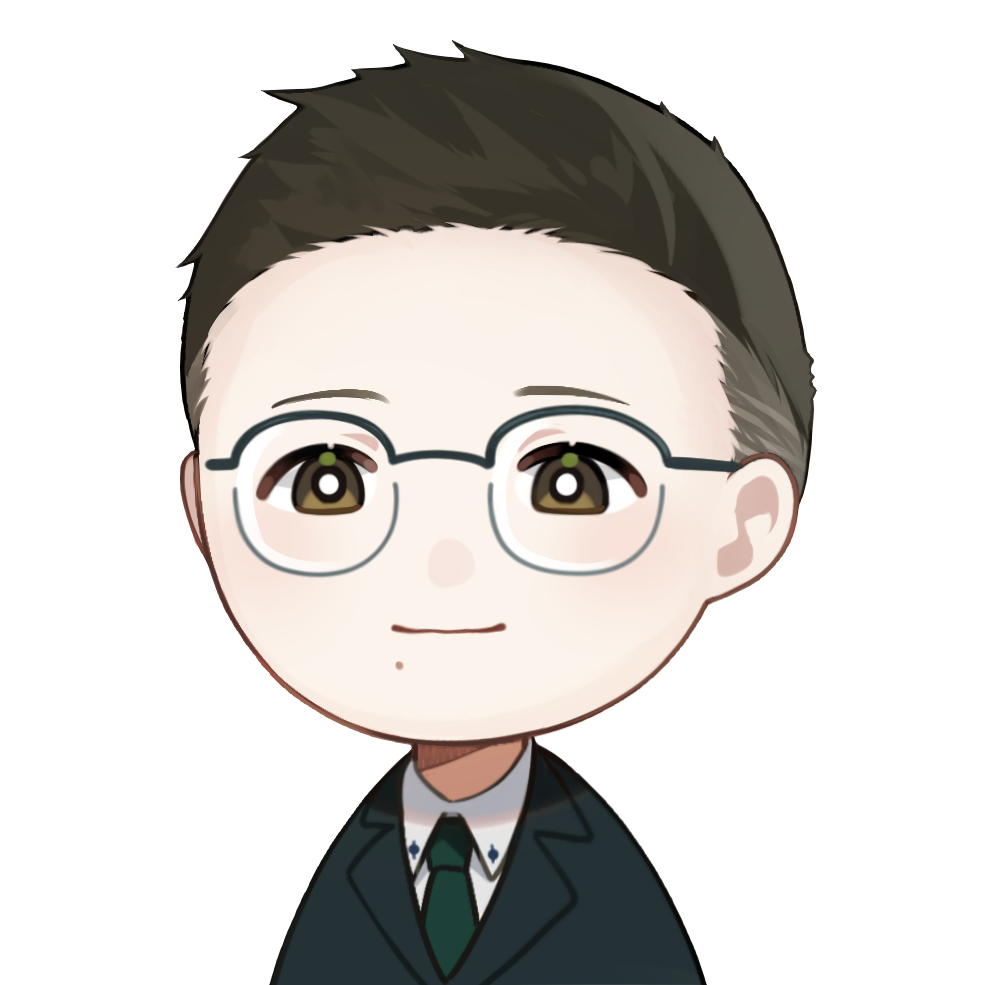
産後うつになりやすい時期があります。産後1〜2週間から数ヶ月以内が多く、症状としては「気分が沈む」「今まで楽しいと思えていたことが楽しいと思えない」「食欲が落ちる」「不安や焦りの気持ちが高まる」「自分に価値を見いだせなくなる」などです。
産後うつとは得体の知れない不安があるような「メンタルヘルスが不調なこと」を表します。
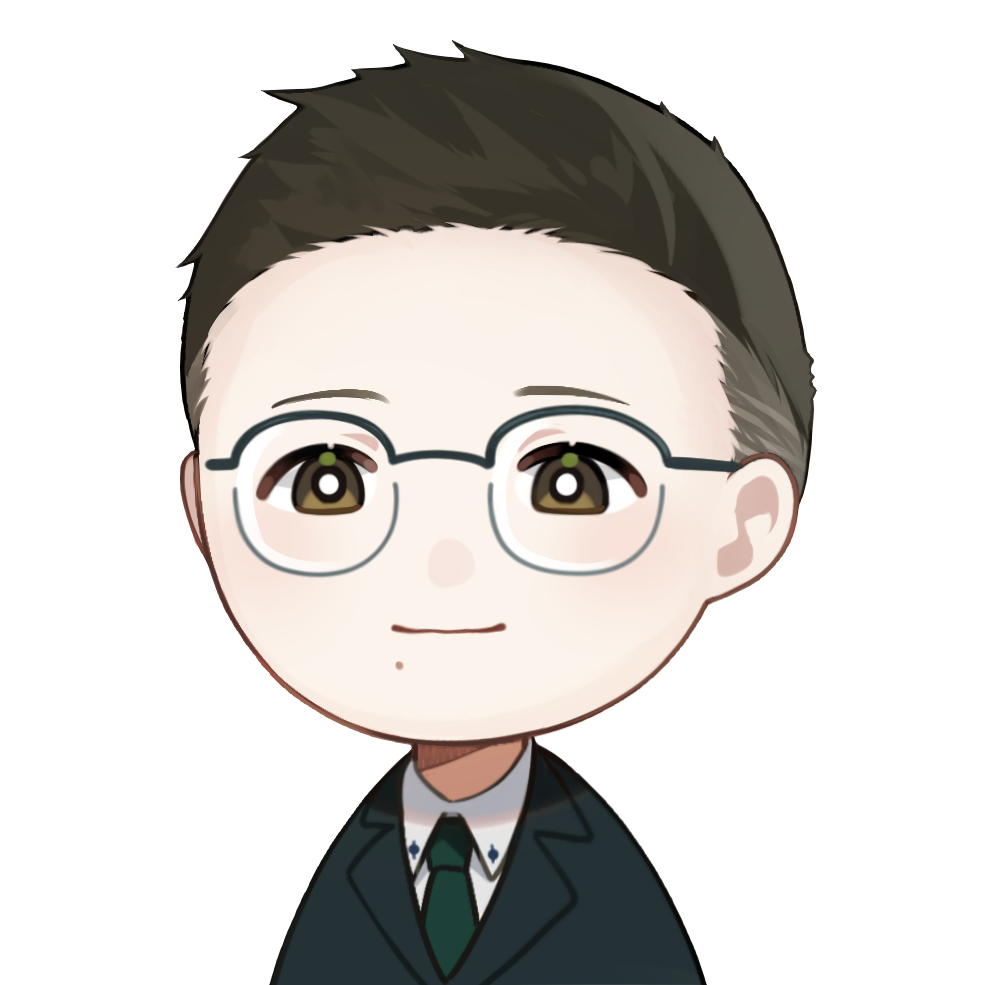
産後うつを引き起こす大きな3つのリスクがあり、
・夫との関係、家族関係、親族関係、経済状況、産後の支援体制などの「社会的支援の不足」
・統合失調症、うつ病、パニック発作、学生時代の摂食障害などの「精神疾患の既往」
・流産、死産、人口死産、兄弟姉妹の死、両親の死などの「精神的に大きな負荷のかかるライフイベント」
などが関わったりします。産後うつと診断された患者さんが医療機関で薬を使った治療だけでは本当の解決にはならないかもしれません。


どうすればいいのでしょうか?

3大リスクをしっかりと理解した上で、もし社会的支援の不足に問題があれば市町村と連携して支援サポートを導入していくことを検討しますし、これまでに精神疾患の病歴があった場合には、その精神疾患の治療の見直しが必要です。死産などの経験で精神的に大きな負荷のかかるライフイベントがあった場合にはカウンセリングをしていくなど、妊産婦さんのお話をよくお聴きすることを大切にしていきます。

やはり傾聴が大切なんですね。
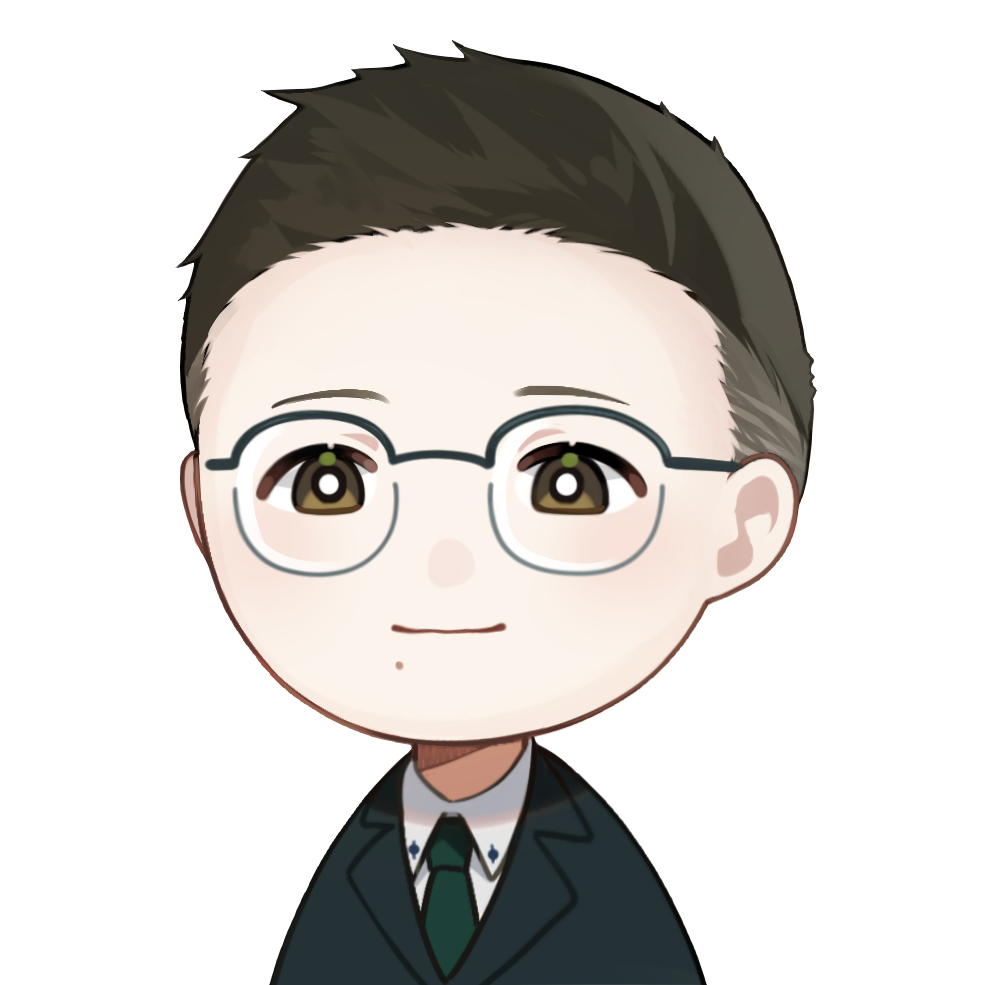
産後うつに付随して、「切れ目のない支援」をなくしていくことが私たち看護職者が気をつけなければいけない部分です

切れ目のない支援とは具体的にどのようなものでしょうか?
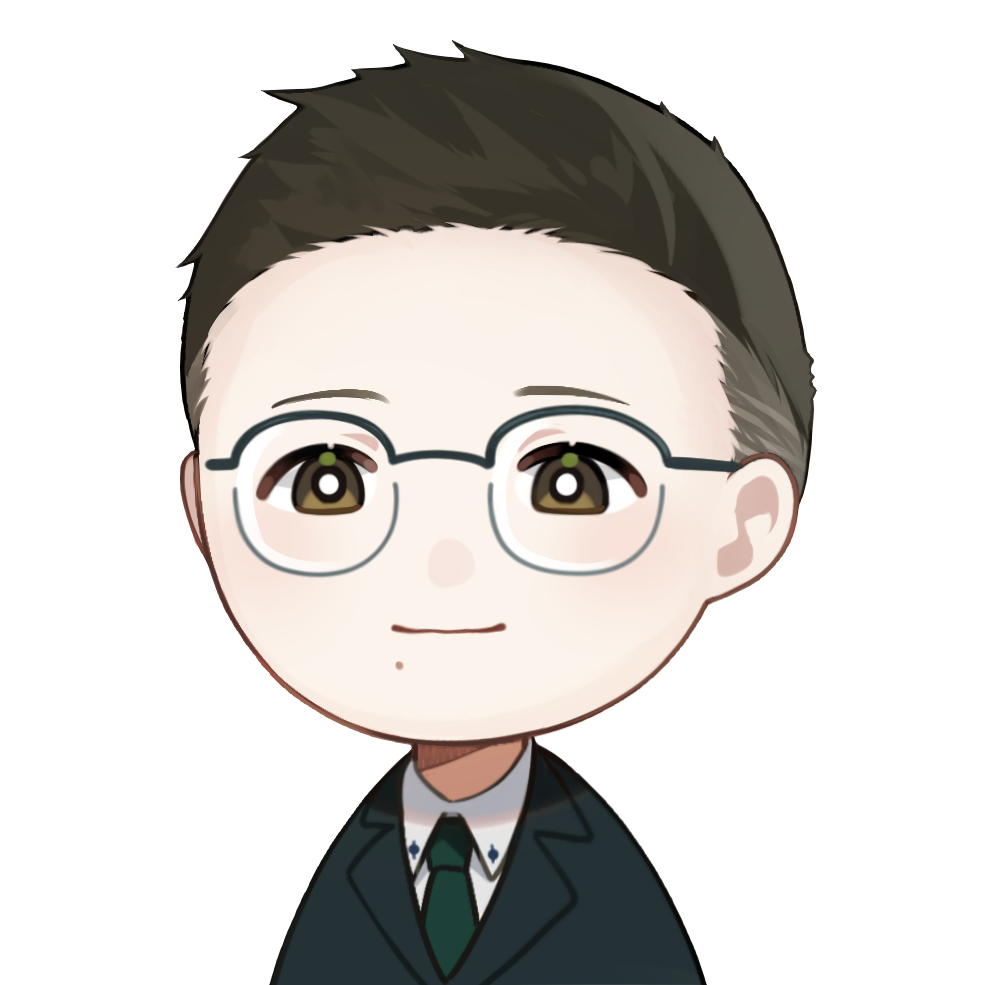
「切れ目のない支援」とは、まず一つが行政のチェックシートの「切れ目」(漏れ)です。子ども虐待による死亡事例のデータを見ていきます。令和3年度は心中以外の虐待死50人のうち、0歳児が24人と全体の48%とという数字が出ています。
要保護児童対策地域協議会といって要支援児童や特定妊婦を早期発見や適切な保護を図るため,児童相談所や学校・教育委員会,警察等の関係機関が子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくために各市町村に設置されているのですが、令和3年度は虐待死50人のうち要保護児童対策地域協議会に関わっていた人数が16人と全体の30%でした。残り70%が要保護児童対策地域協議会から漏れていた(気づくことができなった)ということになります。


支援から漏れてしまう人がいるんですね。
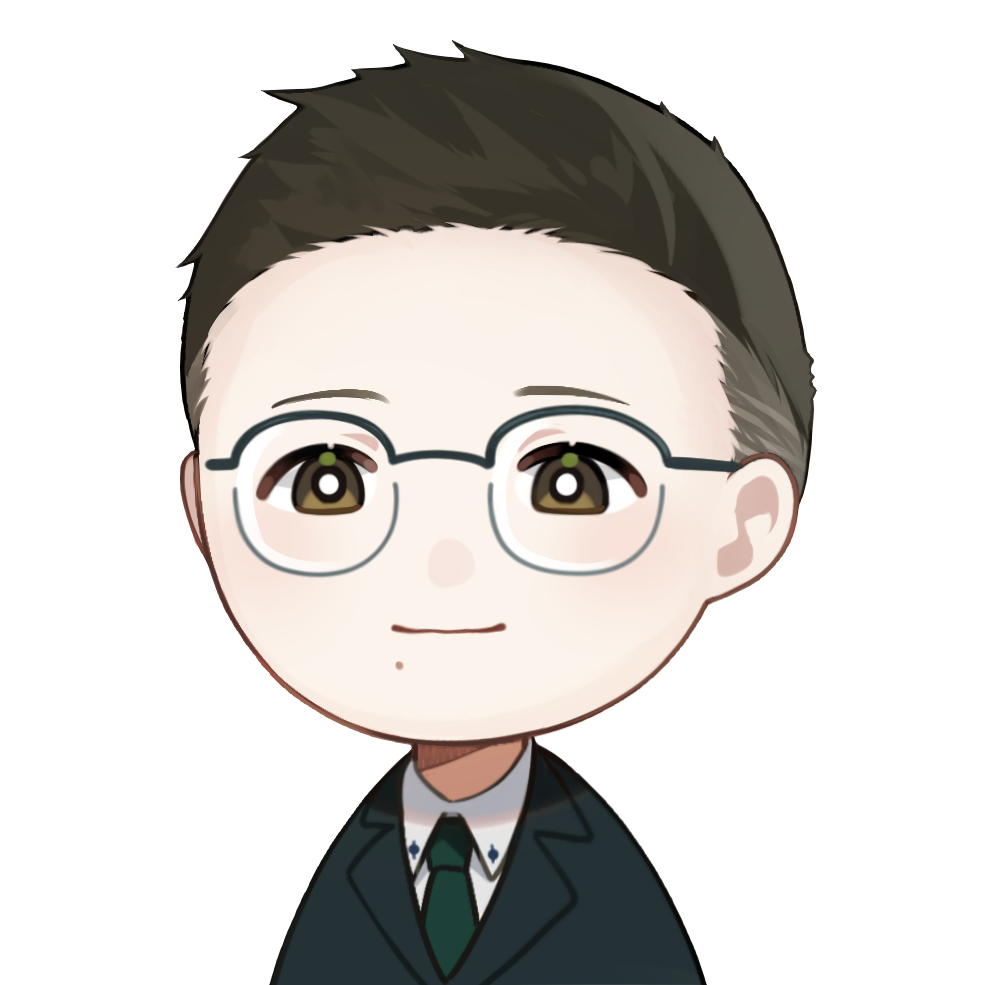
そうなんです。
どういう方が漏れやすいのかというと、架空症例として、妊娠がわかった時点では妊婦さんは幸せと感じていたけれど、悪阻の頃から体調の変化で気持ちの浮き沈みが出始め、気分が落ち込んだ時に今までの過去の辛い経験が思い出されネガティブな感情になってしまう。妊婦さんの感情を妊娠初期と後期で比べると、精神状態が著しく変化し自殺願望を持つほど変わってしまうという場合もあります。
そういったケースにいち早く気づくためには難しいところではありますが、私たち周産期メンタルヘルスに関わる人は「母子の命を食い止められる」という意識を持つべきなんだろうと思います。

なるほど。
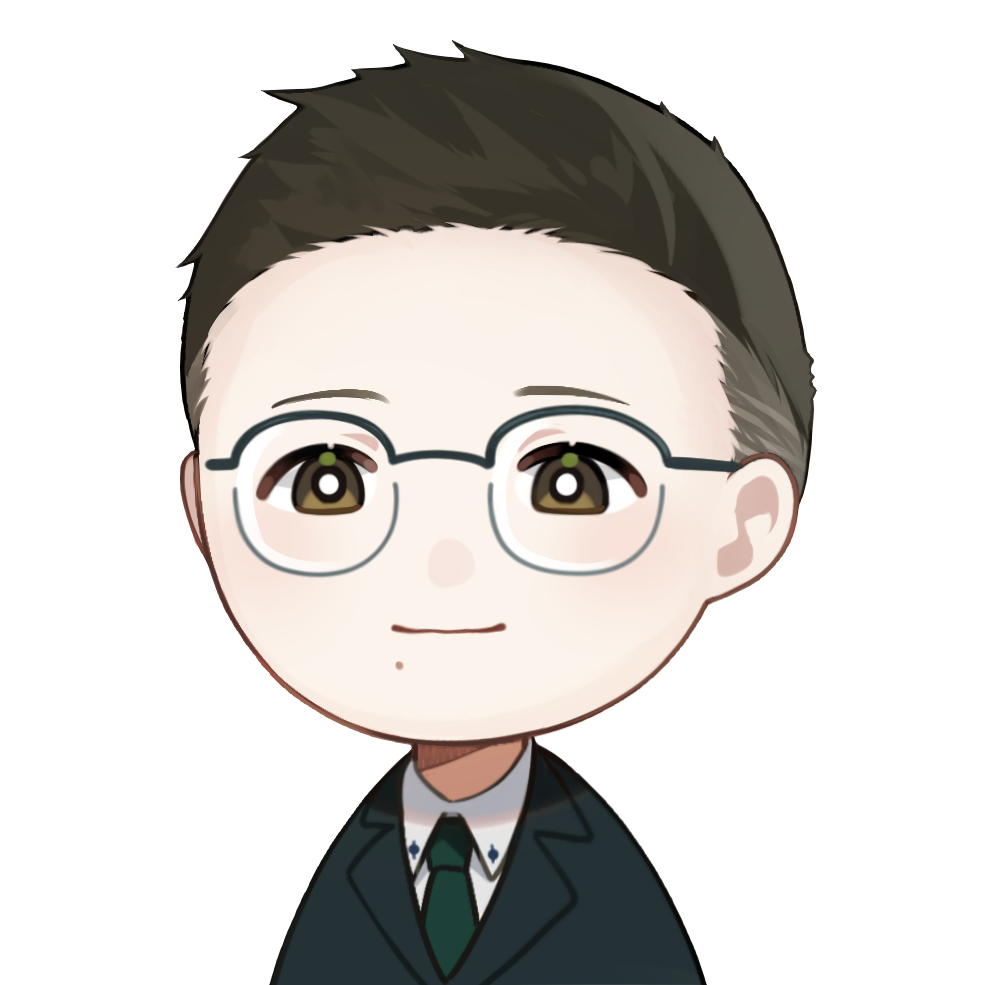
こういった「見えない」症例に向き合うために具体的にどうしたらいいのかというと、妊婦健診や母子健康手帳を渡すタイミング、新生児訪問などあらゆる場面で異変に気づいていかなればなりません。気になる妊婦さんに対してうまく言語化できなくてもこの異変の「勘」をつかむのが大事になってきます。もちろん「勘」だけで動くことは危険ですが、感じた「勘」をチームメンバーと共有し、その「勘」が確かなものなのか確認することで「勘」が鋭くなってきます。一番大切なことは「勘」を共有できるチームメンバーとの雰囲気作りが大事になってきます。

チームワークが大切なんですね。

二つ目は「時間軸の切れ目」です。時間軸の切れ目の部分で一番気になっているのが流産・死産を経験した女性です。令和2年度子ども・子育て支援推奨調査研究事業でのデータでは、
・流産、死産を経験した女性で辛さを感じていた方は直後では93%
・1年〜調査現在においては32.2%
・死産を経験した方では70%
の方がまだ辛さを抱えている状態となっています。
ですが、死産の辛さを癒す時間もなく不妊治療の年齢制限を踏まえて次の妊娠に向かわなければならないという状況の方もいらっしゃいます。

心の傷を癒す時間がないのですね。
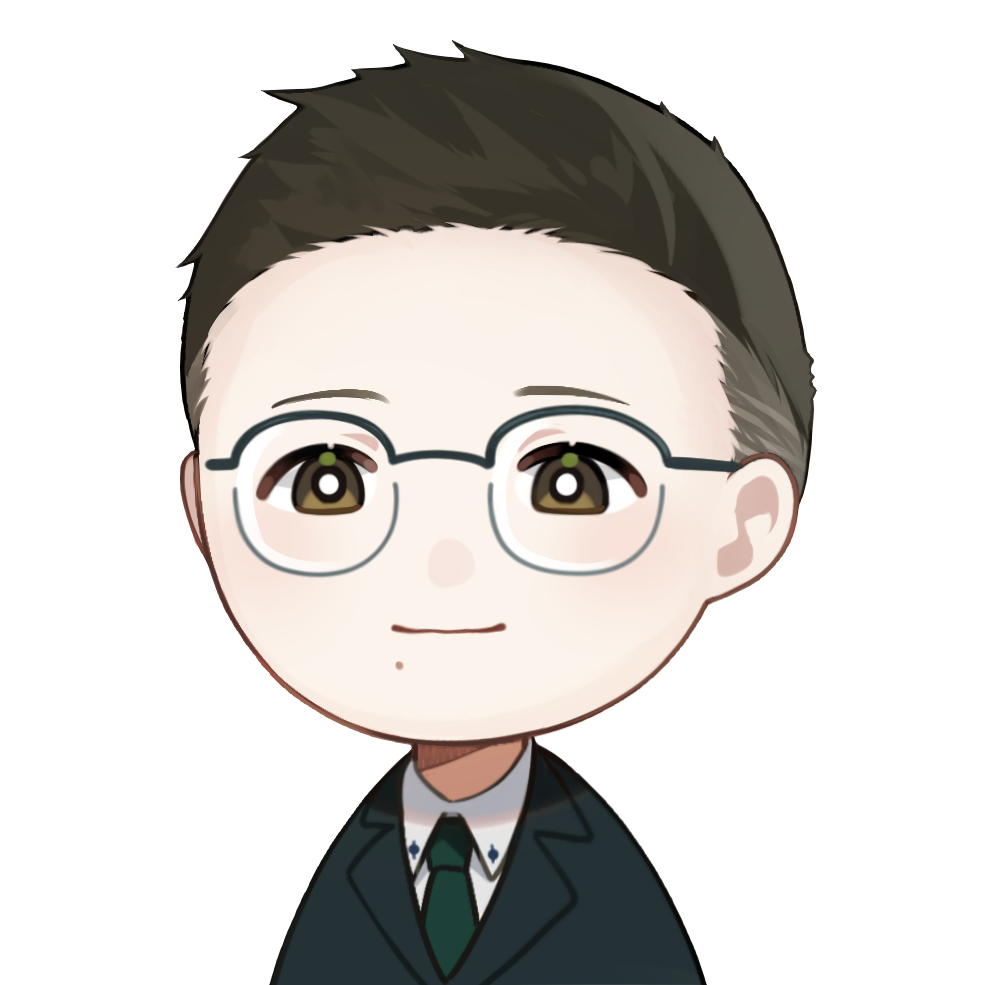
だからこそ、流産、死産を経験した女性に対して伴走型支援が必要となってきます。各市町村においては相談窓口やピアサポートを案内するするなど、きめ細やかな配慮を行うことになってはいますが、現場ではどうなのかというと、先ほどの令和2年度子ども・子育て支援推奨調査研究事業でのデータでは、流産・死産を経験した女性のなかで
・誰かにもっと話を聞いて欲しかった、相談したかったと回答した方 93%
さらに
・行政の相談窓口に相談した方 5.2%
という数字が出ています。つまり、90%以上の方が流産・死産を経験した女性は相談したかったのに相談できていないというのが現実です。
各市町村のピアサポーターの方など地道にがんばっていらっしゃるのですが、まだまだ妊産婦さんへのメンタルの支援が追いついていないのが現状になっています。
このように様々な切れ目を補うように、医療機関、行政など私たち周産期メンタルヘルスに関わる人たちはチームを組み、どんな支援ができるのか状況と妊産婦さんや周りの家族の背景を傾聴することで最善策を提案していくことを続けていきたいです。
